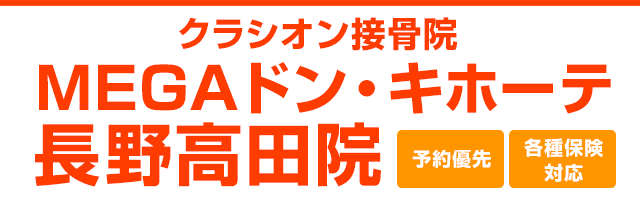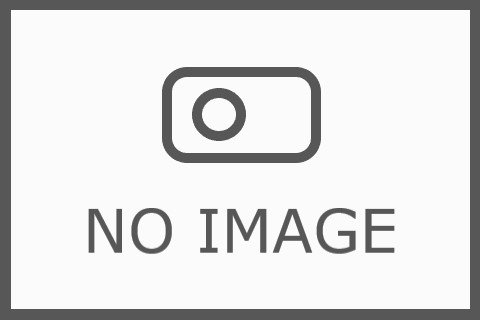肉離れ

こんなお悩みはありませんか?

急にダッシュやジャンプをした時、またはジャンプの着地の際に太ももやふくらはぎに痛みが出てしまう
ストレッチ不足でスポーツなどを行った際に痛めてしまった
痛めた瞬間にプチっと音がした
急に痛みが走り、その後運動などを続けることができなくなった
筋肉の疲労が溜まった状態でスポーツなどを行ってしまった
患部を押すと強い痛みが出る
痛めた付近の関節を曲げ伸ばしした際に痛みが出る
同じ部位で肉離れが起こりやすい
肉離れで知っておくべきこと

肉離れとは、正式には筋挫傷と呼ばれる状態です。スポーツ中などに無理な動作や体勢を急にとった際に、筋肉が損傷・断裂することを指します。発症すると激しい痛みが生じ、それ以上の運動が困難になる場合があります。また、患部にくぼみや変色が現れることもあります。
肉離れが起こるメカニズムとしては、筋肉が強く収縮する際に逆方向へ強く引き伸ばされることで発症しやすいと考えられています。具体例としては、急なダッシュやジャンプ、ジャンプ後の着地時などが挙げられます。
また、肉離れが特に起こりやすい部位としては、太ももやふくらはぎなど、足の筋肉が挙げられます。
症状の現れ方は?

症状の現れ方としては、先述のとおりスポーツ中などに急に筋肉が引き伸ばされ、筋肉が損傷または断裂してしまうことがあります。その際には、強い痛みが出現します。
損傷の程度にもよりますが、多くの場合、そのままスポーツを継続することは難しく、歩行にも影響が出ることがあります。また、損傷部位にはくぼみが見られたり、内部出血による皮下出血斑が見られる場合もあります。
肉離れが起こった後は、患部を押したり付近の関節を動かした際にも痛みが出現するようになります。そのため、肉離れを起こしてしまうと強い痛みとともに、日常生活にも支障が出てしまうことがあります。
その他の原因は?

その他の原因として、筋肉の状態によっても肉離れのリスクが変わります。運動を行う前にストレッチやウォーミングアップが不足していると、筋肉の伸縮力が低下した状態となり、肉離れが起こりやすくなります。また、筋肉に疲労が溜まっている状態や筋力が低下している状態でも肉離れのリスクが高く、柔軟性が低い場合にも同様にリスクが高まると考えられます。
さらに、肉離れを起こした筋肉はクセになりやすく、同じ部位で再び肉離れが起こることがあります。この場合、筋肉の損傷が完全に回復していない状態で再発してしまうケースが多いです。そのため、日頃からのストレッチや定期的な運動が大切です。
肉離れを放置するとどうなる?

肉離れを放置すると、後遺症が残るケースがあります。後遺症としては、血腫や瘢痕組織が形成され、筋肉のつっぱり感やしこり、違和感が残ることがあります。また、これらが原因となり筋肉に負荷がかかり、肉離れを繰り返し引き起こしやすくなる場合もあります。
そのため、肉離れは完治するまでしっかりと対処を行うことがとても大切です。また、肉離れは重症度によってⅠ型からⅢ型に分類されます。それぞれの重症度によって対処法や後遺症のリスクが異なるため、肉離れが起こった際には、まずどの段階にあたるかを把握することが重要です。
当院の施術方法について

当院での施術方法については、まず受傷から48時間以内であればアイシングを行います。筋肉の炎症が起こっている状態なので、冷やすことで炎症を抑えることが期待できます。
その後、損傷した部位が早く回復するように電気施術を行います。電気の刺激による効果として、組織の修復が促されるほか、痛みの原因となる物質の減少が期待されます。
また、指圧などで血流を促進する施術も取り入れています。この血流促進による回復効果も重要です。さらに、痛みが取れた後は、肉離れの再発予防や後遺症を防ぐために、身体の柔軟性を高める筋膜ストレッチという施術も行っています。
改善していく上でのポイント

肉離れの軽減を図る上でのポイントは、発生後いかに早く対処を行うかという点です。
まず肉離れを起こしてしまった場合には、RICE処置を行います。これは重症度に関係なく、肉離れ時に行うことで早期回復が期待できます。RICEとは、安静(Rest)、冷却(Icing)、圧迫(Compression)、挙上(Elevation)の頭文字を取ったものです。
また、肉離れの場合には痛みが気にならなくなったとしても、つっぱり感やしこりなどの後遺症が残る可能性や、繰り返し損傷するリスクがあります。そのため、油断せず適切なケアを続けることが大切です。
監修

クラシオン接骨院 MEGAドン・キホーテ長野高田院 院長
資格:柔道整復師
出身地:北海道小樽市
趣味・特技:映画鑑賞、空手